- ■ 知らないうちに、変わっていく日本の地図
- ■ かつてのゴルフ場跡地、いま“外国資本の街”へ
- ■ 行政の立場:「許可していない」しかし止められない
- ■ すでに100件超の苦情、SNSで加速する“情報の炎上”
- ■ 外国資本はなぜ地方を狙うのか
- ■ 「外国資本=悪」ではない。しかし、“不透明さ”が問題
- ■ 土地規制法の“穴”──朝倉は監視対象外
- ■ 九州各地に広がる“静かな外資の波”
- ■ 変わる地域社会:「観光」から「定住」へ
- ■ メディアの課題:事実報道が“政治化”されている
- ■ 専門家の見解:「透明化こそ最大の防衛」
- ■ 行政に求められる“説明責任”
- ■ 結論:これは“外国資本問題”ではなく、“情報空白問題”だ
- 💬 あなたはどう思いますか?
■ 知らないうちに、変わっていく日本の地図
「最近、町の景色が変わった」――福岡県朝倉市の住民がそう感じ始めている。
筑後平野の北端に位置するこの地は、かつて広大なゴルフ場として利用されていた丘陵地帯。
今、その跡地に14階建て×2棟、計290戸の巨大マンション建設計画が進行している。
事業主体は中国籍オーナーの企業グループ。
入居予定者のおよそ8割が中国・香港・台湾などの出身者だと報じられている。
SNSでは「数万人規模の中国人が移住」「県知事が許可した」などの投稿が拡散し、
地域には動揺と不信が広がった。
しかし、福岡県は「開発許可は出していない」と明言。
実際のところ、何が起きているのか。
取材を進めると、**“土地の自由化”と“行政の無力”**という、日本社会の深層構造が見えてきた。
■ かつてのゴルフ場跡地、いま“外国資本の街”へ
問題の土地は、バブル期に造成されたゴルフリゾートの跡地。
バブル崩壊後は閉鎖され、長年放置されてきた。
その後、国内企業が買収を試みたものの資金が続かず、
最終的に中国系企業が関連法人を通じて取得。
登記上は日本法人だが、出資者は海外資本。
こうして“合法的に”土地の所有権が移転していった。
地元住民はこう語る。
「最初はゴルフ場の再開発かと思った。まさか外国人向けマンションになるとは…」
「夜になると工事車両が動いている。説明が何もない。」
行政からは未だに詳細な説明が行われておらず、
住民説明会も不十分なまま。
一方で、現場の測量や造成作業は静かに進んでいるという。
■ 行政の立場:「許可していない」しかし止められない
福岡県の担当部署は、
「開発許可は出していない。正式な申請があれば審査する段階」
と説明するが、申請前の土地造成行為は監視が難しいという。
日本の都市計画法・建築基準法では、
「事前に許可が必要」な工事と、「申請不要な範囲での造成」が曖昧に分かれている。
これを利用すれば、“許可前の準備行為”として事実上の開発が進行できる構造になっているのだ。
住民が県庁に問い合わせても、
「現段階では違法と断定できない」
との回答しか返ってこない。
その間にも土地は整地され、
周辺の環境は変わっていく。
■ すでに100件超の苦情、SNSで加速する“情報の炎上”
2024年9月以降、SNS上では朝倉市のマンション計画をめぐり、
「中国資本による移住計画」「外国人自治区ができる」といった投稿が急増した。
動画や地図を添えた拡散が相次ぎ、
一部メディアもそれを引用して報じたことで、情報が一人歩き。
福岡県庁にはわずか数週間で100件を超える苦情・通報・問い合わせが寄せられた。
「なぜ外国資本を許すのか」
「行政は何をしているのか」
「安全保障上の問題ではないのか」
だが、県側の回答は一貫して「事実関係を確認中」。
つまり、法的に“止める根拠”がないのだ。
■ 外国資本はなぜ地方を狙うのか
外国資本が朝倉のような地方都市を狙う理由は、
「安さ」と「自由さ」にある。
① 円安で“土地が安い”
1ドル=150円を超える円安が続く中、
日本の不動産は海外投資家にとって実質3割〜5割引きで買える。
② 外国人の土地購入に“制限がない”
OECD諸国の中でも、日本は土地購入の自由度が極めて高い。
登記簿上は日本法人名義でも、資金の出所を追う権限は行政にない。
③ “インバウンド+不動産”の新モデル
観光客ではなく「長期滞在型富裕層」をターゲットにした
“住まう観光”モデルが中国・東南アジアで拡大している。
朝倉のような自然豊かな地域は、そのモデルにピッタリだ。
■ 「外国資本=悪」ではない。しかし、“不透明さ”が問題
開発を進める企業は、形式上は合法的に登録された日本法人。
また、雇用や地域経済への波及効果を期待する声もある。
しかし、問題は開発の目的と情報の非公開性だ。
「どんな人が住むのか、どんな施設になるのか、何も分からない」
地元の不安は、外国人への偏見ではなく、
**行政・事業者の説明不足による“見えない不安”**なのだ。
■ 土地規制法の“穴”──朝倉は監視対象外
2021年に施行された「重要土地等調査法(いわゆる土地規制法)」では、
防衛施設や原発、国境離島周辺の土地取引を監視対象にしている。
だが、朝倉市のような内陸部の住宅開発エリアは完全に対象外。
つまり、仮に外国資本が広大な土地を買っても、
国も県も「調査・制限する法的根拠を持たない」。
法の“空白地帯”が、
地方開発の舞台を外国資本に開放してしまっているのが現実だ。
■ 九州各地に広がる“静かな外資の波”
朝倉の事例は、九州における広範なトレンドの一部に過ぎない。
-
熊本県阿蘇市:中国資本が温泉リゾート用地を買収
-
大分県由布市:湯布院周辺で外国資本の宿泊開発計画
-
鹿児島県霧島市:外国人向け別荘地が拡大中
-
佐賀県唐津市:漁港近くで外国法人が土地を取得
地価が安く、観光資源があり、交通の便が良い――
これらは外国資本にとって“理想的な条件”だ。
■ 変わる地域社会:「観光」から「定住」へ
外国資本の流入がもたらすのは、単なる観光開発ではない。
「外国人が暮らす町」そのものが生まれつつある。
九州では、すでに外国人労働者や技能実習生が地域に定住し、
学校・医療・行政窓口などの“多文化化”が急速に進行している。
朝倉の開発計画も、その延長線上にある。
観光から生活インフラへ。
それは、町の文化と構造を根本から変える可能性を秘めている。
■ メディアの課題:事実報道が“政治化”されている
近年、外国資本や移民に関する報道は、
SNSで瞬時に“愛国/排外”の構図に分断されてしまう傾向がある。
一方、行政発表は慎重すぎて情報が遅く、
結果として“真偽不明の情報”が先に拡散してしまう。
「県が隠している」「報道が忖度している」という陰謀論的な解釈が、
不安をより増幅させる悪循環を生んでいる。
事実を冷静に可視化する報道――
それこそが今、最も求められている。
■ 専門家の見解:「透明化こそ最大の防衛」
九州大学・都市政策学の准教授はこう指摘する。
「外国資本の土地取得を排除するのではなく、
誰が、どこを、どんな目的で所有しているのかを“見える化”することが重要。
透明性が担保されれば、地域社会は適切に対応できる。」
実際、欧州各国では土地所有データを公開し、
住民・行政・報道が共有する仕組みを導入している。
日本も、同様の「土地情報の開示・監視システム」の整備が急務だ。
■ 行政に求められる“説明責任”
朝倉市はこれまで、「県の判断を待つ」という立場に留まっている。
だが、現実に町が変わっていくのは行政区の最前線であり、
説明・調整を行う責任もまた地方自治体にある。
「地域の不安は外国人への敵意ではない。
行政の不透明さへの怒りだ。」
この声に、どこまで応えられるかが試されている。
■ 結論:これは“外国資本問題”ではなく、“情報空白問題”だ
朝倉の開発をめぐる議論は、
「外国人が土地を買った」という単純な話ではない。
-
行政が市民に情報を開示できない
-
法制度が時代に追いついていない
-
SNSが空白を埋め、誤情報が広がる
この3つの構造が、
日本各地で“同じ不安”を生み出している。
問題は「誰が土地を買ったか」ではなく、
「なぜ何も知らされないのか」。
💬 あなたはどう思いますか?
-
外国資本の地方進出、どこまで認めるべき?
-
「土地は誰のものか」という問いに、国はどう答えるべき?
-
情報を公開せず、曖昧なまま進む開発をどう止めるか?
👉 コメント欄で、あなたの意見を聞かせてください。
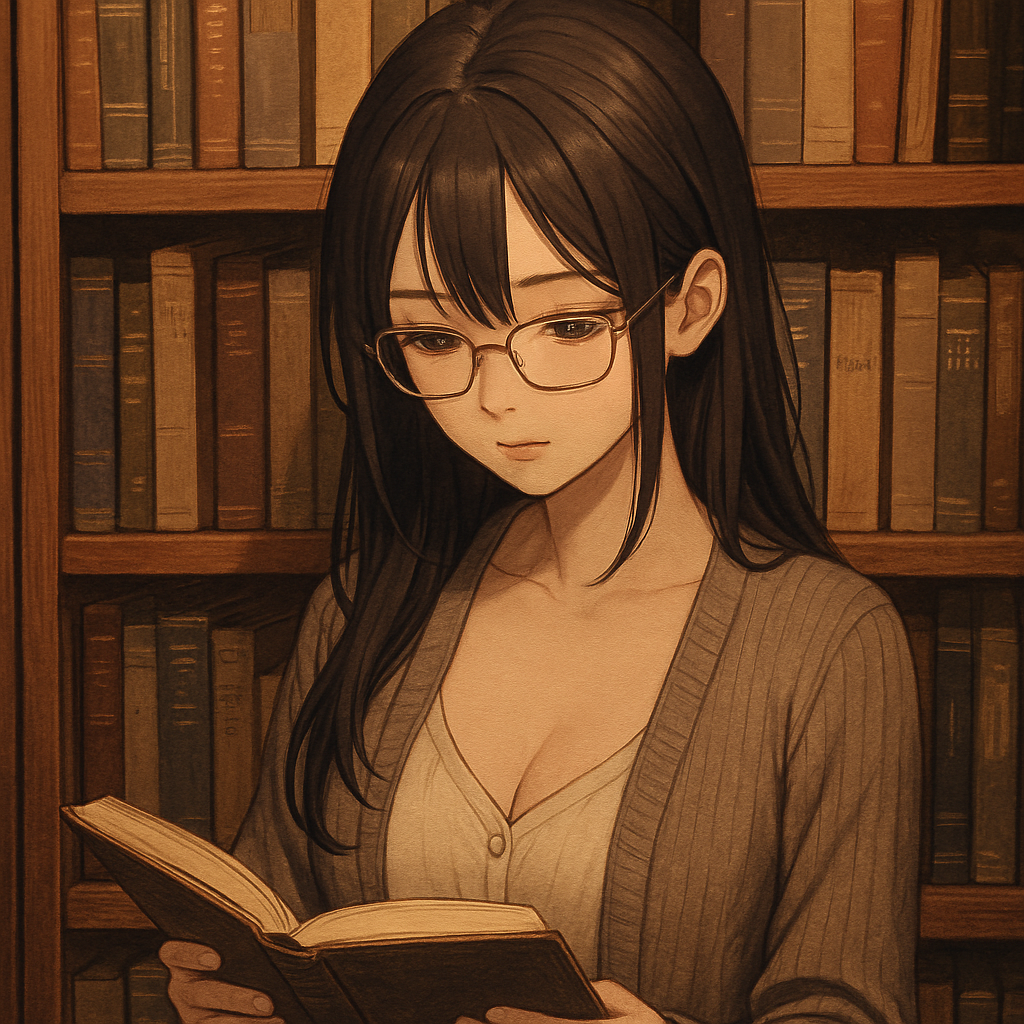
「知らなかった」から「動く」へ。
外国人問題・土地買収・移民政策のリアルを追いかけ、
署名活動や住民の動きを発信するブログです。
SNSでも動画で拡散中(YouTube・Instagram・TikTok)。
日本の未来を守るために、あなたの意見が力になります。




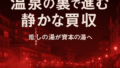
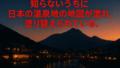
コメント