■ クマ出没最多で報じられる今、見落とされてきた“異変”
最近、北海道・東北地域で野生のクマの出没件数が増加傾向にあります。
ニュースでは「人里近くにクマが」「住民が危険にさらされている」という見出しが並びます。
しかし本質を見れば、クマの数が“増えた”のではなく、
**“人がいなくなった山や森”**が増えているのです。
人が管理してきた山林が、所有者の変化や放置によって
“人の手の届かない森”へと変化してきました。
■ 外資による山林・森林取得の最新データ
最新の調査によれば、
2024年だけで国内の私有森林地を 382ヘクタール にわたって外国人や外国法人が取得していると報じられています。 JAPAN Forward+2MDPI+2
中でも北海道が大きな割合を占め、ツーリズム地・別荘地・未開発地が中心です。 JAPAN Forward+1
例えば、ある報道では以下のように記述されています。
「北海道では36件、162ヘクタールの森林が2024年に外国の住所をもつ買い手によって取得された」 JAPAN Forward
「2006年~2024年で、10,396ヘクタールが外国人・外国法人の所有になった」 JAPAN Forward
また、農地についても、2024年には 175.3ヘクタール が外国人・外国法人に取得されたというデータがあります。 JAPAN Forward
こうした数字は、決してごく小規模ではなく、東京ドーム数十個分の土地が対象となっています。
■ 法制度の隙間に入る“放置された森”
日本では、外国人・外国企業による土地購入は基本的に自由です。
森林法・農地法・外資規制など、複数の法律がありますが、外国所有を根本から制限する規定はほとんど存在していません。
例えば、森林に関しては、外国法人が取得しても「使用目的が森林維持」である限り、規制対象になりにくいという指摘があります。 MDPI
また農地は「耕作目的」での取得が原則ですが、2024年には報告制度強化が始まったばかりで、まだ実効性のあるデータが整っていません。 JAPAN Forward
さらに問題なのは、取得された土地がその後「管理されないまま放置」されるケース。
所有者は海外法人である場合が多く、現地常駐者も少ないため、林道整備、定期巡回、伐採管理、住民との連携などが滞ります。
この“人が入らない山林”が増えることで、
森=人の手の届かない“野生ゾーン”
へと変化する構図が浮かび上がってきます。
■ “人がいない森”がなぜクマを増やすのか?
管理の途絶えた山林では、次のような現象が起きます。
-
獣害対策の放棄:罠設置や巣穴監視などがされず、クマの生息数・行動範囲が拡大。
-
人里との境界の曖昧化:人の足が減った山林は、人里の近くでも“クマの出る可能性のある森”へと変化。
-
生態系の変化:旧来人間が関与していた森林管理が停止し、クマを含む大型動物が活動域を広げやすくなる。
-
防衛・監視の欠如:住宅、林道、看板など人の痕跡が薄れると、動物にとって安全な“棲み処”となる。
これらは、単なる“クマの増加”ではなく、**“人口減少・土地所有変化・管理放棄”**という構造変化の表れです。
■ 事例:北海道・ニセコ地域/釧路湿原周辺
ニセコ・ルスツ地域
冬季観光の聖地として知られるニセコでも、外国資本による土地取得が多く報じられています。例えば、森林地の取得・別荘地の転用・未開発山林の所有など。 JAPAN PROPERTY CENTRAL K.K.+2MDPI+2
この地域では、「所有者不明」「税金未納」「用途不明」の土地が増え、地元自治体が対応に追われています。
釧路湿原周辺
世界的に重要な湿地帯である釧路湿原近くでは、メガソーラー建設計画や海外資本の土地取得が進行しています。 ウィキペディア
自然保護と開発の綱引きの中で、人の立入れない山林がさらに広がる懸念があります。
こうした事例は、単に観光地だけでなく、森林・生態系・地域コミュニティの関係性自体を変化させてしまう可能性を孕んでいます。
■ 時事的な背景:人口減少・地方の衰退・国土戦略の変化
日本全体の人口は減少に転じ、地方の自治体では過疎化が進んでいます。
さらに、林業・農業・漁業といった地方産業も衰退傾向にあり、山林の管理体制も縮小しています。
こうした構造の中で、
-
地価下落
-
所有者不明地増加
-
地元住民の山離れ
が同時に進行。
併せて、国家安全保障の観点からも、
外国資本による土地取得や資源アクセスが注目されています。
例えば、防衛施設や航空基地近隣の土地取引を監視する必要性が議論されています。 JAPAN Forward
このため、
森林・山林・水源地=単なる自然資源ではなく、
国家の安全保障・国土保全のフロンティア
として捉え直されつつあります。
■ なぜ“クマの増加”という報道になりがちなのか?
報道の多くは「クマが増えた」「人里に出てきた」という視点に偏りがちです。
しかし、それだけでは真因を捉えきれません。
-
“人がいない森”という背景が抜け落ちている。
-
外資取得・土地放置という構造が語られていない。
-
森林管理放棄=生態系変化という視点が欠如。
こうした欠落が、問題を「動物のせい」「野生化のせい」に矮小化してしまう。
結果として、森の管理者=自治体・民間・住民の役割が曖昧になってしまうのです。
■ 今、地域社会が迫られていること
1.土地情報の可視化
取得者・用途・管理状況が不明の山林・森林について、国・都道府県・市町村によるデータ整備が急務です。
報道ベースでも「所有者不明」「税金未納」「別荘地化されている」などが指摘されています。
2.管理責任の明確化
山林を取得した企業・法人には、定期巡回・植生管理・獣害対策・地域協議といった“管理義務”を課す必要があります。
所有=管理義務という原則を法整備で明文化すべきです。
3.地域参画による森林再生
住民・自治体・林業関係者・環境団体が協働して、
「無人化した森」を地域資源として再構築する仕組みが求められています。
クマ出没対策、防災林整備、体験型ツーリズムなどがその一環です。
4.安全保障視点の導入
森林・山林・水源地の所有変化は、単なる不動産取引ではなく、
国の“国土保全・防衛”の観点からも捉え直す必要があります。
特に、基地や通信施設、交通網の近傍土地における外資取得は、
透明化・監視強化の対象にすべきです。
■ 結論:「人が山を捨てた」とき、森が答えを出す
クマが出た、という言葉だけでは、
この現象の全体像を捉えるにはあまりに浅い。
本質は、
人のいない山林=管理のない自然=所有者のいない土地
という“制度的空白”にあります。
このまま進めば、クマだけでなく、
人間の”領域”さえ、静かに変容していくのかもしれません。
私たちは、森を守るというだけでなく、
**“誰が土地を所有し、誰が管理し、誰が住むか”**を問い直す時代に入っています。
クマが増えたのではない。
人が山を手放したのです。
💬 あなたはどう思いますか?
-
外資による山林・森林取得をどう捉えますか?
-
森林の管理責任を所有者・自治体・地域、どこに置くべきでしょうか?
-
“人がいない森”“所有者不明地”が広がる日本で、自然と人はどう向き合うべきだと思いますか?
👉 コメント欄で、あなたの意見を聞かせてください。
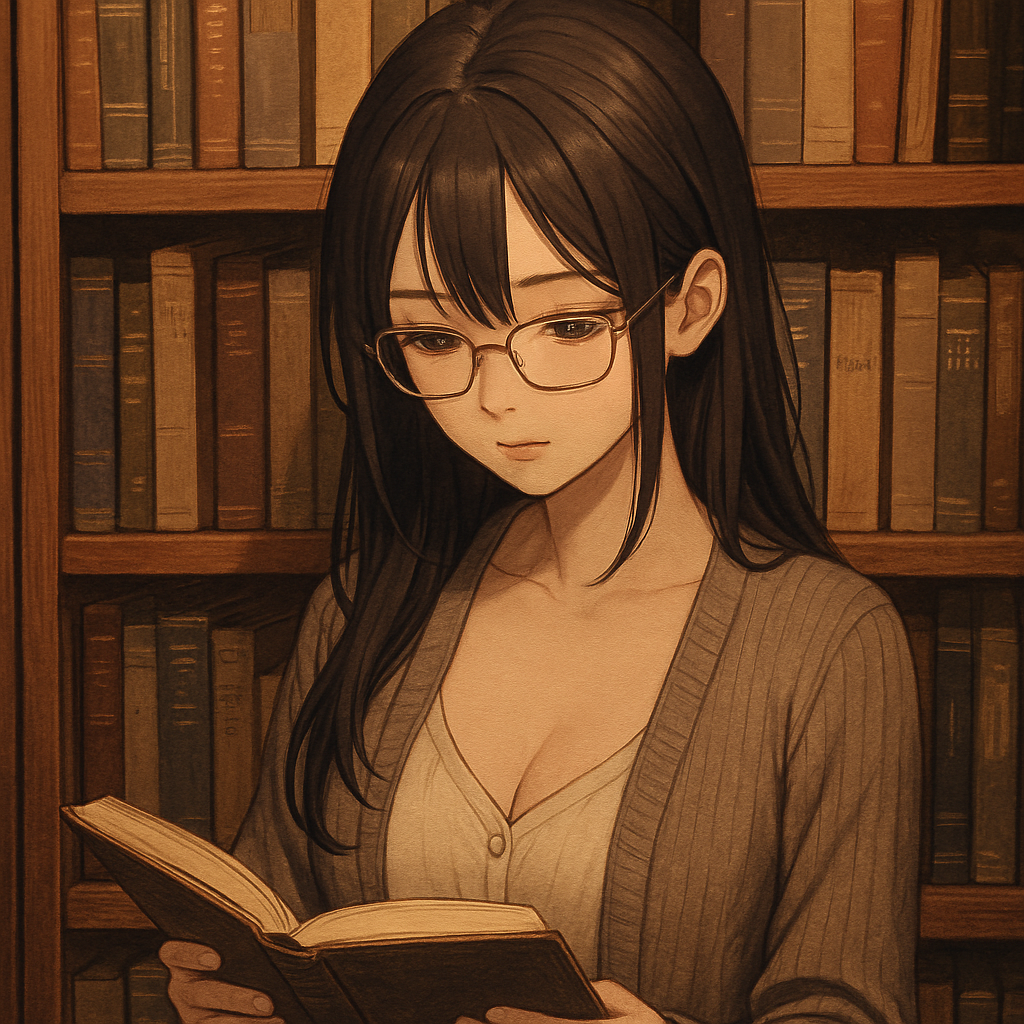
「知らなかった」から「動く」へ。
外国人問題・土地買収・移民政策のリアルを追いかけ、
署名活動や住民の動きを発信するブログです。
SNSでも動画で拡散中(YouTube・Instagram・TikTok)。
日本の未来を守るために、あなたの意見が力になります。





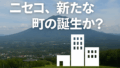
コメント