■ 静かな住宅街に突如浮上した「インド系スクール計画」
札幌市のある地域で、にわかに注目を集める一件があります。
それは、廃校となった小学校跡地を利用して建設が進められている「インド系インターナショナルスクール」計画です。
当初、札幌市はこのプロジェクトを「地域の国際化」「教育の多様化」「経済活性化のチャンス」として打ち出しました。
説明資料には「グローバル人材育成」「多文化共生」といった、聞こえの良いキーワードが並び、
一見すれば、前向きな未来像を描いた構想に見えます。
しかし、その裏側では、住民たちの強い不安と不信が積もりに積もっていた。
「突然、廃校跡地に外資の学校ができると聞かされた」
「誰が決めたのかも分からないまま話が進んでいる」
行政と地域との間に、見えない壁が生まれつつありました。
■ 住民説明会は混乱──「これは説明会ではなくアリバイ作りだ」
数ヶ月前、札幌市が主催した住民説明会が開催されました。
この日、地域の集会場は満席。
開始前から緊張した空気が流れていました。
登壇したのは、市の担当者と事業者側の代表。
しかし、説明が始まるとすぐに会場はざわつき始めました。
「説明が薄すぎる!」
「そもそも、いつ決まった話なんですか?」
「住民の意見を聞く気があるのか?」
怒号が飛び交い、やがて抗議の声が一斉に上がりました。
SNSでは、参加者がその様子を投稿。
「説明会じゃなくて、ただのアリバイ作り」
「質問しても“検討中です”しか言わない」
「担当者が途中で“体調不良”を理由に退場して、警察まで来た」
という報告が拡散され、
この説明会が**“異常な事態”**だったことが一気に広まりました。
■ 廃校跡地、外資、そして“決まってから説明する行政”
今回の舞台となったのは、かつて地域の子どもたちで賑わっていた公立小学校の跡地。
閉校後も「地域の記憶」として残され、
自治体が「活用先を検討中」としていた土地でした。
そんな中で突然浮上した“インド系スクール計画”。
しかし、住民が知ったのは「ほぼ決定後」だったのです。
「私たちの意見を聞く前に、もう契約が決まっていた」
「説明会は形だけ。すべて出来レースに感じる」
この「事後報告」に、住民たちは激しく反発。
なぜなら、この土地は地域の税金で整備された公共資産だからです。
にもかかわらず、行政と外資の間で水面下の交渉が進み、
地域住民はただ「説明を受けるだけの存在」にされてしまった。
■ “透明性が大事”という言葉だけが、虚しく響く
札幌市は繰り返しこう発表しています。
「透明性を重視しており、今後も住民との対話を続けてまいります。」
だが、その“透明性”はどこにあるのか。
説明会で住民が求めたのは具体的な事実です。
-
契約内容と資金の流れ
-
運営主体の実態
-
土地利用期間と更新条件
-
治安や交通への影響予測
-
将来的な再売却の可能性
これらの質問に対して、行政側の答えはどれも曖昧でした。
「まだ検討中です」
「今後の協議で詰めていきます」
つまり、「説明」はしたが、「答え」はしていない。
市民が求めたのは“透明な行政”ではなく、“誠実な対話”だったのです。
■ 外資導入=悪ではない。だが、“決め方”が間違っている
ここで誤解してはいけないのは、
多くの住民が「外国人」や「インド系学校」に反対しているわけではないということです。
反対しているのは、“決め方”です。
「国際化そのものには賛成。だけど、筋が通っていない。」
「地域の声を無視して進められるのはおかしい。」
札幌市が目指す「多文化共生」や「グローバル教育」は、
理念としては誰も否定しません。
しかし、その理念を実現するプロセスが、
**“地域との合意なきままの導入”では、
多様性ではなく“分断”**を生むのです。
■ 「外資による土地利用」のリスク──全国で進む“見えない所有構造”
日本では、外国資本による土地取得や長期貸与が増えています。
とくに北海道では、ここ10年で水源地や山林、スキー場の外国買収が相次いでいます。
夕張市:スキーリゾートとホテルが中国系企業に売却
赤井川村:周辺の森林が外国資本に買収される
ニセコエリア:不動産の約半分が外国人オーナー
札幌市も例外ではありません。
今回の廃校跡地も、インド資本による長期貸与契約が検討されています。
問題は、「土地利用の透明性がないまま外資が入る」こと。
一度契約が成立すれば、所有権や利用権の追跡が極めて困難になるのです。
つまり、「誰が何の目的で土地を使っているのか」が、市民には分からなくなる。
この“見えない所有構造”こそ、地方自治の盲点です。
■ 廃校の活用が「財政補填」の道具になっていないか
廃校の再利用は全国で進んでいます。
しかし、その多くが「地域再生」ではなく、実際は財政難の補填策となっています。
自治体が維持費削減を最優先するあまり、
事業の実効性よりも「すぐに借り手がつく」ことが重視される。
「金になるなら、誰に貸してもいい」
「地域の意見を聞いていたら時間がかかる」
この思考が、外資との不透明な契約を生む背景になっています。
札幌も例外ではありません。
「グローバル教育」という理想の影で、
**“財政合理化のための外資導入”**が静かに進んでいる。
■ 「説明した」で終わらせてはいけない
札幌市の対応を見ていると、どこかの行政文書のように感じます。
「説明責任は果たしました」
「住民意見は参考として伺いました」
だが、それは対話ではなく手続きです。
形式的な説明会を開き、
「説明した」という実績を残せば、それで終わり。
けれど、住民が求めているのは**“参加”**なのです。
決定の前に、声を届ける機会。
その仕組みがない限り、何度説明会を開いても信頼は戻りません。
■ 国際化は「共に決める」ことから始まる
本来の「国際化」とは、外国資本を導入することではなく、
地域社会が多様性を受け入れる準備をすることです。
教育も、街づくりも、
“誰かが決めて与える”ものではなく、“一緒に考える”ことから始まる。
「外国人を排除したいのではない。
地元の未来を他人に決められたくないだけだ。」
この声に耳を傾けずに「多様性」を掲げても、
それは“言葉だけの共生”にすぎません。
■ 行政への信頼が崩れたとき、何が起こるのか
説明不足、強行的な進行、外資との密約――
これらが積み重なると、最も深刻なのは**「行政への信頼の崩壊」**です。
信頼が失われた瞬間、
市民は“行政の発表”を信じなくなる。
そして、情報はSNSや口コミで拡散し、
憶測や誤解が現実を上書きしていく。
札幌で今まさに起きているのは、
「情報空白」が生んだ不信の連鎖です。
■ 結論:このまま進めていい話なのか?
札幌市は「今後も透明性を確保して進める」と述べています。
だが、説明会で示されたのは、言葉だけの透明性でした。
地域の人々が求めているのは、“共に考えるプロセス”。
それを失ったまま進む「国際教育プロジェクト」に未来はあるのでしょうか。
「多様性」とは、声を聞くこと。
「透明性」とは、情報を隠さないこと。
それを忘れた行政に、地域の信頼は戻りません。
💬 最後に
あなたはどう感じますか?
このまま進めていい話だと思いますか?
それとも、立ち止まって見直すべきだと思いますか?
コメント欄で、あなたの意見を聞かせてください。
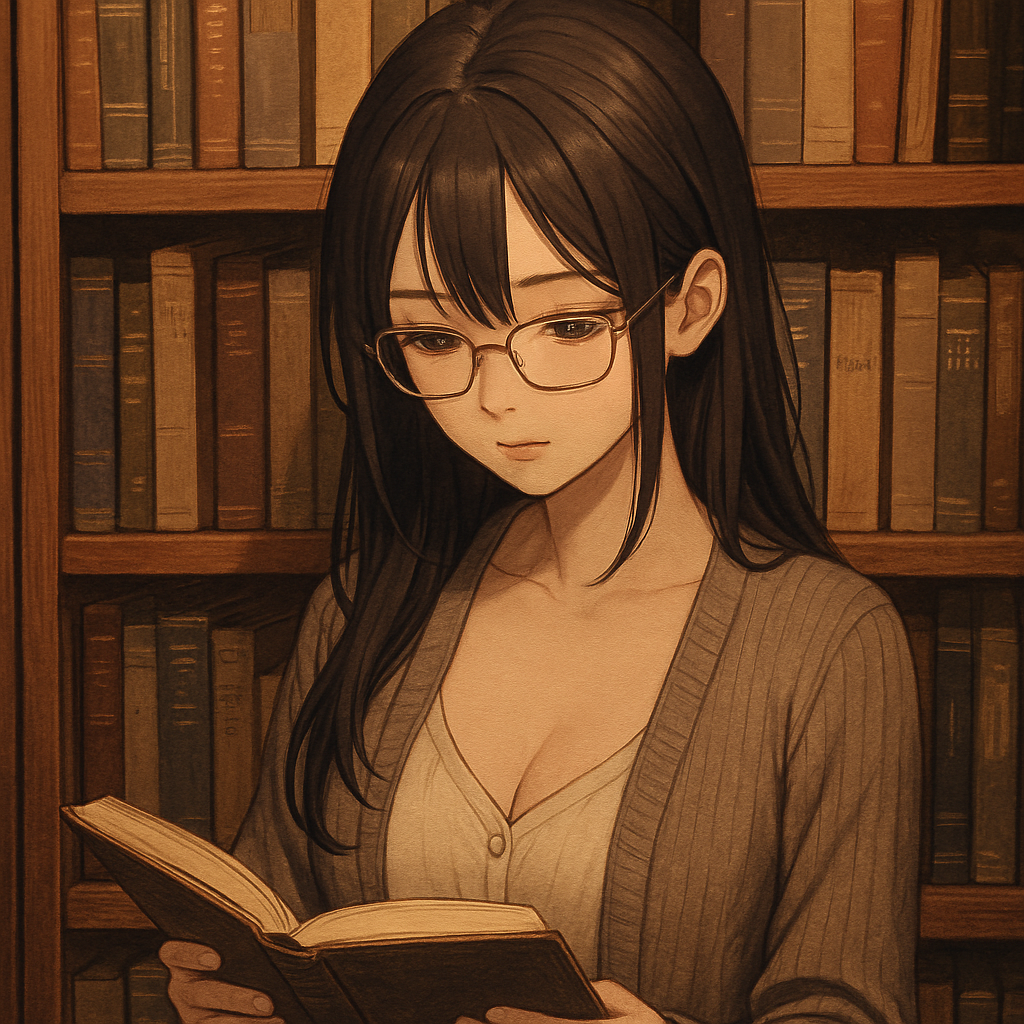
「知らなかった」から「動く」へ。
外国人問題・土地買収・移民政策のリアルを追いかけ、
署名活動や住民の動きを発信するブログです。
SNSでも動画で拡散中(YouTube・Instagram・TikTok)。
日本の未来を守るために、あなたの意見が力になります。





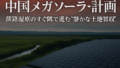
コメント