■ 炭鉱の街から“観光都市”へ。夕張が歩んできた激動の半世紀
かつて夕張は「石炭の町」として知られ、日本のエネルギーを支えた存在でした。
最盛期の人口は約12万人。しかし、炭鉱閉山とともに経済は急速に縮小し、財政赤字が膨らみ、2007年には全国初の**財政再生団体(実質的な破綻自治体)**に指定されました。
以降、夕張市は「観光での再生」を掲げ、外部企業との連携に活路を見出します。
その象徴が、マウントレースイスキーリゾートの再開発でした。
■ 2019年、マウントレースイスキー場の売却と外資の参入
2019年、夕張市が所有していたスキー場とホテルが、中国系企業グループにおよそ2億円で売却されました。
この金額は国内のリゾート開発案件としては非常に低額であり、背景には「財政再建中で早期の現金化が必要だった」という事情があったといわれます。
買収後、企業グループは施設の再整備を進めつつ、関連会社を通じて周辺の土地取得にも動いていると報じられています。
この再開発には「観光客誘致」だけでなく、長期的な土地投資の意味合いも含まれていると指摘されています。
■ 北海道全体で進む「外国資本による土地取得」
夕張の事例は孤立したものではありません。
北海道では近年、外国企業やファンドによる土地取得が各地で確認されています。
-
ニセコ:スキーリゾート周辺の土地を外国資本が次々と購入
-
千歳:自衛隊基地周辺に外国企業が土地を保有
-
占冠(トマム):大規模な森林や山林を海外企業が取得
-
北見・釧路周辺:再生可能エネルギー関連企業による山林取得
これらの取引はすべて合法です。
日本では外国資本による土地所有を規制する法律が存在しないため、水源地や森林地帯でも自由に売買が可能なのです。
■ 水源地と土地が注目される理由
なぜ“水源地”が注目されるのでしょうか。
-
豊富で清浄な水資源
北海道は全国屈指の降水量と広大な森林を持ち、地下水や河川が豊富です。
これらは飲料水・農業・発電など多方面に利用価値があります。 -
地価が安く、取得コストが低い
人口減少と過疎化で、地方の山林価格は下落しています。
外国企業にとっては、将来の“水ビジネス”や“土地担保”として魅力的です。 -
規制が緩く、所有後の管理が曖昧
取得後の用途制限がほとんどなく、森林の伐採・転売・貸出も自由に行えます。
こうした要因が重なり、北海道は「資源としての土地」を狙う投資家にとって理想的な市場となっているのです。
■ 夕張でも見られる「観光と資源保有の二層構造」
夕張では、表向きは“観光再生”が掲げられています。
しかし、その裏で、観光施設の周辺地や山林の所有権が徐々に外国企業の手に移っているという指摘もあります。
これはニセコやトマムと同じ構図で、
「観光客を呼び込むことで土地価値を上げ、最終的には資産として保有する」
という戦略です。
地元住民の中には、
「中国語の看板が増え、地元よりも外から来た人の影響が強くなった」と話す声もあります。
一方で、市の関係者は「外資は必要なパートナー。観光で再生するためには避けられない選択」とも語ります。
つまり、夕張は再生と侵食の狭間に立たされているのです。
■ 「土地利用規制法」導入後も続く課題
2021年に施行された**重要土地等調査法(いわゆる土地利用規制法)**では、
自衛隊や原発、水源地など重要施設の周囲を対象に、外国人や外国企業による土地利用を調査できるようになりました。
しかし、
-
規制区域の指定が限られている
-
監視や報告が“事後対応”中心
-
地方自治体には実質的な権限がない
という課題も多く、夕張のような観光目的の取引は対象外になりやすいのが実情です。
そのため、実効性を疑問視する声も少なくありません。
■ 観光再生か、地域主権の喪失か――岐路に立つ夕張
外資の力でインフラや施設が整備され、観光客が戻る。
それは短期的には地域の利益になります。
しかし、土地や資源の所有権が海外に移れば、
将来的に「地域が自分たちの資産を自由に使えない」状況が生まれる可能性もあります。
行政が破綻した街ほど、再開発には外部資本が入りやすく、
結果的に「自治の力が縮小する」という構造的リスクを抱えます。
■ 夕張の未来を考えるために必要な視点
-
外資導入を全面否定するのではなく、透明性を高めること。
契約内容や所有構造を地元住民が把握できる仕組みを作るべきです。 -
水資源や森林の保全を、自治体単独でなく道・国レベルで管理すること。
個別の市町村では追跡も規制も不可能です。 -
「観光で再生」と「土地の主権を守る」の両立を目指す。
観光開発が進んでも、土地や水が地域の共有資源であるという原則を忘れてはなりません。
■ 結論:夕張は“地方再生の試金石”であり、“国土管理の警鐘”でもある
夕張のケースは、単なる地方の観光開発ではありません。
それは、日本の土地・水・資源をどう扱うのかという国家的なテーマを突きつける象徴的な事例です。
観光による経済再生は歓迎すべきことです。
しかし、
「誰が土地を持ち、誰が資源を管理するのか」
この問いを放置したままでは、真の地方創生にはなりません。
■ あなたはどう考えますか?
-
外資による観光再開発は地方の希望か?
-
それとも、地域主権を失う始まりか?
-
「土地の所有」と「地域の未来」をどう結びつけるべきか?
コメント欄で、あなたの意見を聞かせてください。
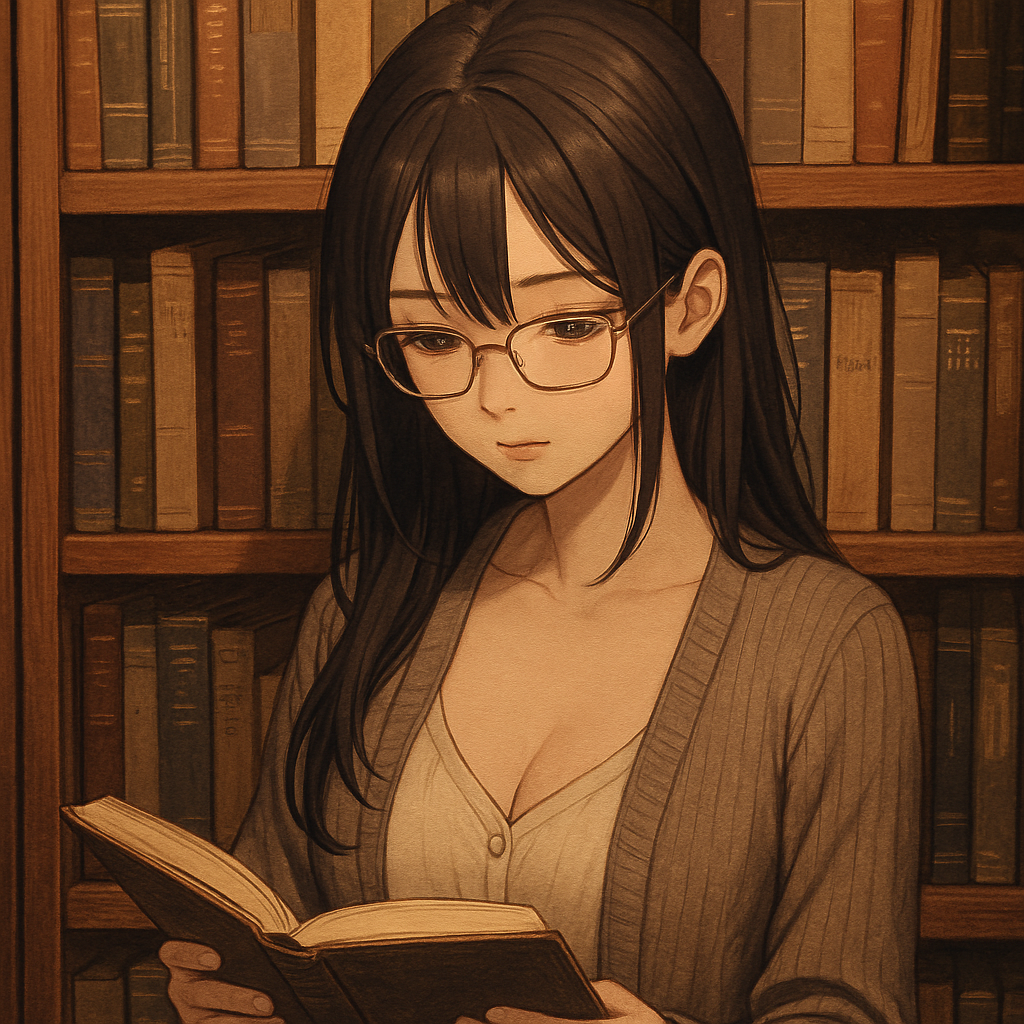
「知らなかった」から「動く」へ。
外国人問題・土地買収・移民政策のリアルを追いかけ、
署名活動や住民の動きを発信するブログです。
SNSでも動画で拡散中(YouTube・Instagram・TikTok)。
日本の未来を守るために、あなたの意見が力になります。





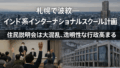
コメント