■ 序章:支援の裏で取り残される日本の若者
最近、SNSでは「外国人留学生への支援が手厚すぎるのでは?」という声が増えている。
学費免除、毎月の生活費支給、家賃補助――これらの制度の存在を知る人はまだ少ない。
一方で、日本人学生の多くは奨学金という名の借金を背負い、社会に出るころには数百万円の返済を抱えている。
同じ国の若者でありながら、なぜこんなにも扱いが違うのか。
■ 日本の教育費は、世界でも異常に高い
OECDの調査によれば、日本の大学授業料は世界でもトップクラスの高さだ。
アメリカと並んで「教育費が家計を圧迫する国」として知られている。
ヨーロッパでは無償化や給付型奨学金が主流だが、日本では「教育は自己責任」という考え方が根強い。
結果として、努力しても“貧困の再生産”から抜け出せない若者が増えている。
■ 奨学金の正体は“教育ローン”だ
「奨学金」という言葉の響きは柔らかい。だが実態は、利息付きのローンに過ぎない。
日本学生支援機構(JASSO)の調査によると、卒業時点での借入額は平均300万円を超える。
返済が滞れば延滞金が加算され、場合によっては信用情報に傷がつく。
社会人になっても結婚・出産・住宅購入など、人生の選択が常に“借金残高”に縛られる。
努力して大学を出た若者が、社会に出る前から「負債者」として扱われる――これが今の日本だ。
■ 外国人留学生への支援は国家戦略、だが…
外国人留学生に対しては、文部科学省の「国費留学生制度」などで、
学費免除・毎月12〜15万円の生活費支給・宿舎提供など、手厚い支援が行われている。
これは日本が「優秀な海外人材を取り込みたい」という国家戦略に基づくものだ。
だが、問題はその裏で日本人学生の支援が圧倒的に少ないという現実である。
奨学金返済に苦しむ日本人学生を救う制度は乏しく、
「留学生を助けて、日本の若者は自力でなんとかしろ」という構図が生まれている。
■ 政府の“多様性”政策は誰のためか?
最近よく聞く言葉が「多様性」と「共生社会」だ。
だが現実は、美しいスローガンの裏で国内の若者が疲弊している。
多様性は素晴らしい。だが、誰かの犠牲の上に成り立つ“共生”は本当の共生ではない。
「外国人を受け入れろ」という前に、
まず自国の若者が安心して学べる社会を作るべきではないのか。
■ 日本の教育支援がここまで歪んだ理由
なぜこうなったのか。
根本にあるのは「教育を投資ではなく“個人の責任”とみなす社会構造」だ。
企業は即戦力を求め、政府は人材育成に金を出さず、
親は「奨学金を借りるのは当然」と諦める。
そして若者は、
「大学を出ても貧困」
「努力しても報われない」
「夢より返済」
という現実に押しつぶされていく。
■ 奨学金という鎖が人生を縛る
奨学金返済が原因で結婚を諦める人、
子どもを持つことをためらう人が増えている。
中には、返済を理由に自殺を選ぶケースすらある。
それでも制度は「自己責任」で片づけられる。
いつからこの国は、若者の夢を借金に変える国になったのか。
■ 支援のバランスを正せ
外国人留学生の支援をやめろ、という話ではない。
必要なのは「同等の機会を日本人にも用意する」ことだ。
-
給付型奨学金の拡充
-
利息のない奨学金制度
-
教育費の段階的無償化
-
奨学金返済免除の条件緩和
これらを本気でやれば、日本の若者は希望を取り戻せる。
■ 教育は“投資”であって“負担”ではない
国が教育に投資しなければ、未来を築く人材は育たない。
教育を削り、若者を借金で縛る国家に、発展などあるはずがない。
「努力は報われる」と信じて生きてきた世代に、
その努力の果実を「奨学金の請求書」として突きつける――
そんな社会を放置して、未来を語れるのか。
■ 結論:支援の本当の意味を取り戻せ
日本は今、静かに“教育格差”が広がっている。
それは経済格差だけでなく、「夢を見る自由」の格差でもある。
国が若者を支えない国に、未来はない。
借金ではなく、希望を与える社会へ。
それが、本来あるべき“支援”の形ではないだろうか。
💬 あなたはどう思いますか?
「奨学金制度」「外国人留学生支援」「教育費の格差」――
ぜひコメントであなたの意見を教えてください。
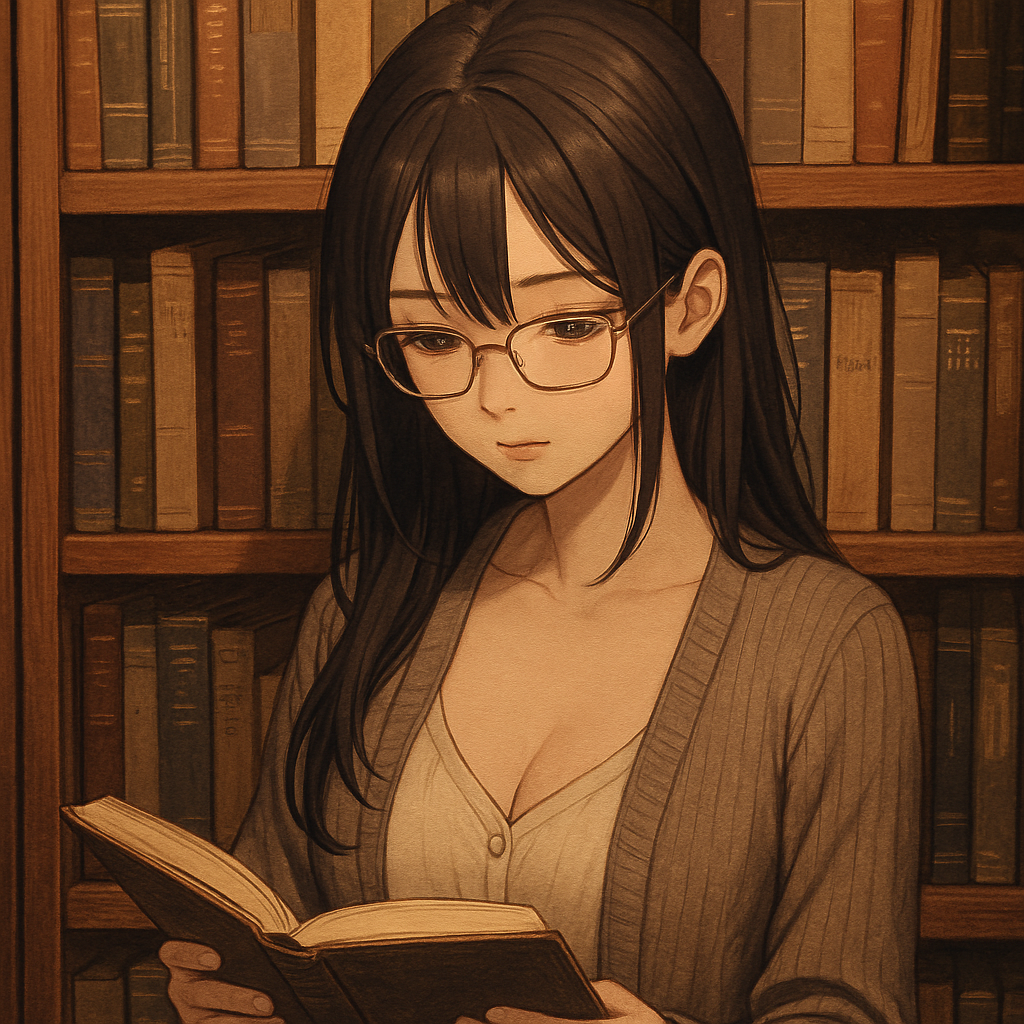
「知らなかった」から「動く」へ。
外国人問題・土地買収・移民政策のリアルを追いかけ、
署名活動や住民の動きを発信するブログです。
SNSでも動画で拡散中(YouTube・Instagram・TikTok)。
日本の未来を守るために、あなたの意見が力になります。




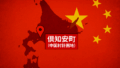

コメント